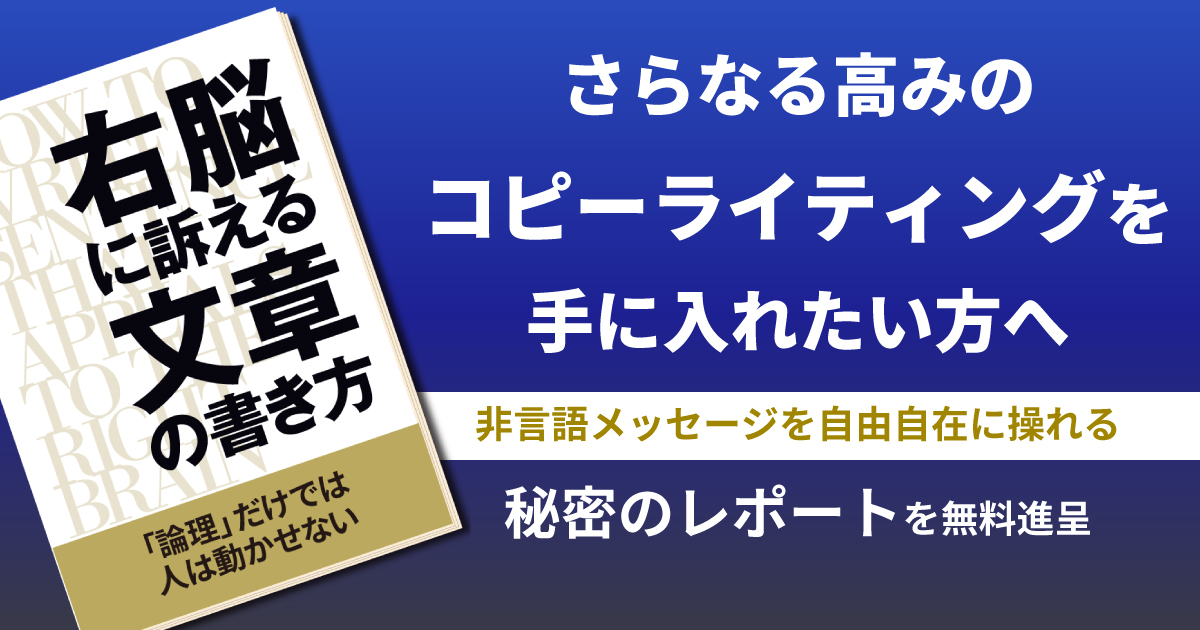「最近のユーザーって、斜め読みして単語だけで拾っている感じがする」
記事LPやLPを書いていて、そんなふうに思ったことはありませんか?
その感覚は当たっています。
ネットユーザーの多くは、文章をほとんど読まず、単語の拾い読みをしているのです。
1年前私は、広告代理店からある記事LPを見せてもらいました。
その記事LPは、論理的に見ておかしな内容でした。しかし、反応がすこぶる良いというのです。
衝撃と同時に、やっぱりなと得心がいきました。
それからも、記事LPの成功例をいくつも見る機会に恵まれ、私も書いてきました。
実践経験から言えるのは、ネットユーザーは以前にも増して、拾い読みをしているということです。
こうした現状は、セールスコピーを書く人にとっては、深刻な課題と言えるでしょう。
せっかく考え抜いて書いたコピーがまともに読まれていないのですから。
そこで今回は、この事象について深く掘ってみたいと思います。

深井 貴明
広島県在住。
1999年から2009年までの約10年間、飲料水・化粧品・医薬部外品・エコ商品などの製造販売会社に勤務。在職中にコピーライティングと出合い、実践と研究を重ねる。FAXDMだけで90日間に1,533件の新規顧客を開拓し、DMのみで1億円の売上を達成するなど、数々の成果を上げる。
2009年より、セールスコピーライター兼コンサルタントとして独立。東証上場企業をはじめ、非上場の大手企業やアフィリエイト専門会社の専属コピーライターとして活動。また、個人事業主から中堅企業まで幅広く広告・販促物の制作を手がけている。
単なるライティングにとどまらず、常にマーケティング戦略の見直しから取り組み、成果へとつながる言葉を生み出すことを信条としている。
単語の拾い読みが増えた5大原因

拾い読みが増えたのは、主に環境要因が大きいです。
その主因は、スマホです。
実は、スマホは紙やPCに比べて、拾い読みをしてしまう傾向があるのです。
スマホがもたらす読み方や読解力について様々な調査報告があります。
調査報告一覧
日付:2018年
研究者名:Patricia Alexander(メリーランド大学)らによるメタ分析(54件・約17万人対象)
論旨:紙の方がスクリーンよりも読解力に優れる傾向
URL:https://www.snexplores.org/article/learn-comprehension-reading-digital-screen-paper
日付:2021年
研究者名:Katsuhiko Ogawa(小川勝彦)ら
論旨:60人を対象とした実験で、60%以上がスマートフォンよりデスクトップ画面で読解・記憶が良好
URL:https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7398
日付:2023年
研究者名:Delphine Gras-Vincendon, Frédéric Pons(仏Université de Bordeaux)ら
論旨(タイトル):2,391人対象調査。説明文ではPCよりスマホ利用時に読解度が有意に低下
URL:https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.236
日付:(2012年〜)学術レビュー
研究者名:Ackerman & Lauterman(2012)、Margolin et al.(2013)、Mangen et al.(2013)など
論旨(タイトル):メタ分析により紙 vs スクリーンでの読解力比較。スクリーン読解が劣る傾向を確認
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reading
2024年7月
研究者名:Ragnhild Engdal Jensen, Astrid Roe, Marte Blikstad‑Balas(オスロ大学)
論旨(タイトル):紙と画面での読解理解、テキスト処理、読書態度の比較
URL:https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.compedu.2024.105107?utm_source=chatgpt.com
これは発表されている調査報告の一例です。
探せばいくらでも出てきます。
これらの調査から、スマホが拾い読みを“助長している”のは確かな傾向だと言えるでしょう。
拾い読みは、これからも加速する!

スマホは2010年以降、急速に普及し始めました。
その頃はあまり拾い読みの傾向を、現場レベルでは感じていませんでした。
特にここ数年で、その傾向が顕著になってきました。
2020年以降から「拾い読みをしているのではないか」と感じるようになったのです。
おそらく、スマホによる弊害が徐々に顕在化してきたのではないかと思います。
というのは、スマホは前頭前野をはじめとした様々な脳機能を低下させることが分かっています。いわゆる、「スマホ脳」「スマホ認知症」です。
つまり、スマホは拾い読みを促すだけでなく、深く読む力自体も奪っていくのです。
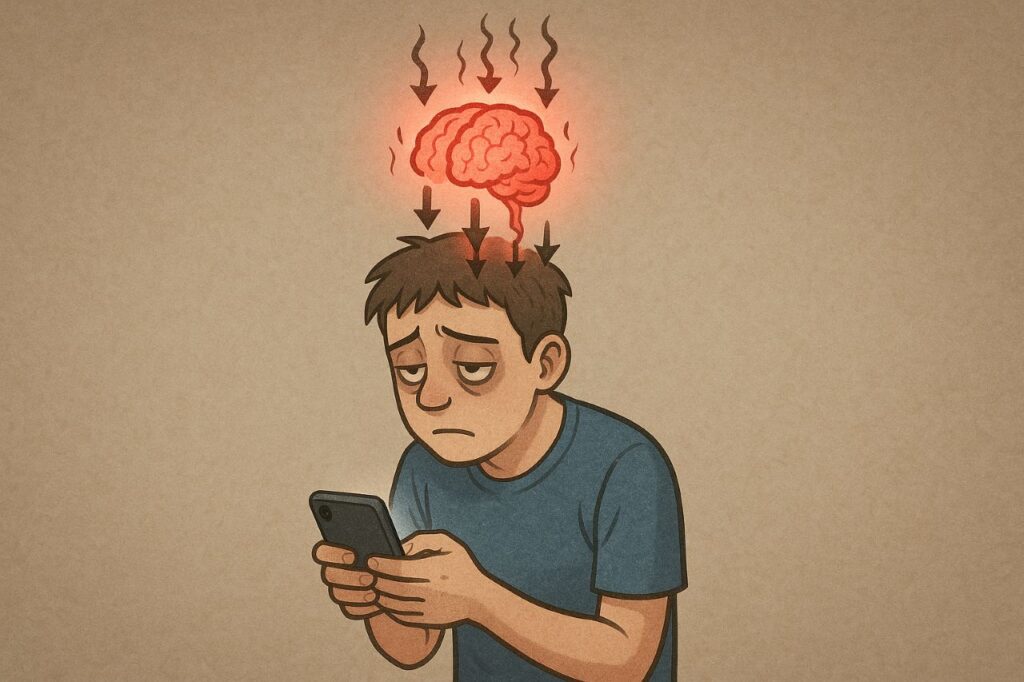
こちらの研究も進んでいます。
調査報告一覧
日付:2022年
研究者名:Kinjari Kancharla, Sagayaraj Kanagaraj, C. Gopal
論旨:スマホの過剰使用は、忘れっぽさ、注意力散漫、誤作動などの認知的失敗と関連しており、認知機能の低下リスクがある。
URL:https://consensus.app/papers/neuropsychological-evaluation-of-cognitive-failure-and-kancharla-kanagaraj/92132cbd8fe35c858cfdf0d357cca0af/?utm_source=chatgpt
日付:2023年
研究者名:Christian Montag, Boris Becker
論旨:MRI研究によって、スマホの過剰使用が脳構造や機能、精神的健康、感情的および認知的能力に悪影響を及ぼす可能性が示されている。
URL:https://consensus.app/papers/neuroimaging-the-effects-of-smartphone-overuse-on-brain-montag-becker/b5fbf48ed50b5ab19eab9f5792d0fd96/?utm_source=chatgpt
日付:2015年
研究者名:Nathaniel Barr, Gordon Pennycook, J. Stolz, J. Fugelsang
論旨:スマホ使用者は直感的な思考に依存しやすく、深く考える(分析的思考)力が低い傾向にある。スマホは「考えることの外部化」を助長している可能性がある。
URL:https://consensus.app/papers/the-brain-in-your-pocket-evidence-that-smartphones-are-used-barr-pennycook/f720577a813f5c9a9261e6dc886541c0/?utm_source=chatgpt
日付:2017年
研究者名:J. Chun, Jihye Choi, Jin-Young Kim, Hyun Cho, K. Ahn, Jong-Ho Nam, Jung-Seok Choi, D. Kim
論旨:過剰なスマホ使用者は、怒りの表情や感情変化に対して前頭前野(DLPFC)と前部帯状皮質(dACC)の活動が低下し、感情の認識や制御が困難になっている。
URL:https://consensus.app/papers/altered-brain-activity-and-the-effect-of-personality-chun-choi/c8c7f1403de4500991ca35d8140add57/?utm_source=chatgpt
日付:2017年
研究者名:A. Hadar, I. Hadas, A. Lazarovits, U. Alyagon, D. Eliraz, A. Zangen
論旨:スマホの長時間使用は右前頭前野の神経活動を低下させ、注意力の低下、衝動性の増加、社会的認知の変化などの認知・感情機能の障害を引き起こす。
URL:https://consensus.app/papers/answering-the-missed-call-initial-exploration-of-hadar-hadas/9babdf3cc483568cb1670d916ff83394/?utm_source=chatgpt
日付:2020年
研究者名:Jaeun Ahn, Deokjong Lee, K. Namkoong, Y. Jung
論旨:スマホ依存者では前頭前野と島皮質、扁桃体間の接続に異常が見られ、感情や行動の調整に関連する脳ネットワークに広範な影響を与えている。
URL:https://consensus.app/papers/altered-functional-connectivity-of-the-salience-network-ahn-lee/a1d544903e9c5e42bed7a3ffd5ffb210/?utm_source=chatgpt
日付:2022年
研究者名:Xinyi Li, Yadan Li, Xuewei Wang, Weiping Hu
論旨:スマホ依存傾向のある人は創造課題中に前頭前野と側頭葉の活動・連携が弱く、創造的思考や認知機能の柔軟性が損なわれている。
URL:https://consensus.app/papers/reduced-brain-activity-and-functional-connectivity-li-li/f8b1af400ff15333ae0d697cb353981d/?utm_source=chatgpt
スマホを手放すことは今の人類には難しいでしょう。
よって、単語の拾い読みの傾向はますます強まると考えていいでしょう。
拾い読みでも購買させるセールスコピー7原則

ユーザーによる単語の拾い読みは、もう避けては通れません。
コピーを書く者は、それを前提にコピーを書いていくしかないのです。
そこで、私が現場で培ってきた、拾い読みでも購買させるセールスコピー7原則をお伝えします。
1.ファーストビューで勝負を決めろ!
売りたい商品の魅力は、すべてファーストビューに詰め込むようにします。
一太刀で勝負を決める覚悟でコピーを書き切るのです。
ファーストビューの役割は注意を引くことだけではありません。興味関心を引くことのも役割なのです。
2.できるだけ見出しを設けるようにする
一つのセクション(見出しから次の見出しまで)が長すぎると、ユーザーはストレスを抱えてしまいます。ユーザーが疲れる前に、次の見出しが現れるようにしましょう。感覚としては、2~3スクロールで次の見出しが来る感じです。
3.画面上には常に画像が来るようにする
単語の拾い読みにおける情報伝達不足を画像を使って補強します。また、画像があることにより読むストレスを緩和させられるため、結果的により長く読んでもらえるようになります。記事LPの場合、画像の頻度は高く、5行以内に画像1枚の間隔で入れてください。
4.強調したい言葉は、目立たせる。
目立たせる手段は、「文字サイズ」「太字」「下線」「マーカー」「文字の白抜き」などがあります。または、目立たせたい一文の前後に余白を作って、目立たせるといった技法も有効です。そして、目立たせた単語だけを拾っても、要点が伝わるように設計しましょう。
5.インパクトのある単語やたとえ話を使う
単語を目立たせるだけではなく、単語自体もインパクトのあるものを使いましょう。たとえ話や比喩を用いれば、インパクトのある単語を使いやすくなります。
6.小まめに改行をして読みやすくする
黒い文字ばかりが詰まった画面は、それだけで読む気を削ぎます。小まめな改行で余白をつくりましょう。ちなみに、小説家・今村翔吾さんも、黒と白のバランスを意識していると語っています。
参考:「漫画の方が小説よりも・・・」直木賞作家の今村翔吾が「創作」について本音を激白【本ツイ!#111】
7.ネットユーザーの目線(F字)に合わせて、左側に強調したい言葉を置く
デバイスを問わず、人は文字を読むとき目線はF字を描きます。
つまり、左側にある単語は視認されやすいわけです。
よって、強調したい単語は左側に置くようにしましょう。
また、左側(文章の始まり)に強い単語を置くことができれば、初頭効果も期待できます。
※初頭効果とは、最初に見たものの印象を強く残す心理作用
まとめ
今のユーザーは、文章を読むのではなく、単語を拾って理解しようとしています。
この傾向は、今後さらに強まると予測されます。
時代に合わせて、セールスコピーも変わっていかなくてはなりません。
これから求められるのは、“読まれなくても伝わる”コピー。
拾い読みされる前提で、伝える構造を組み直すこと。
それが、スマホ時代のセールスコピーの標準になります。